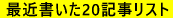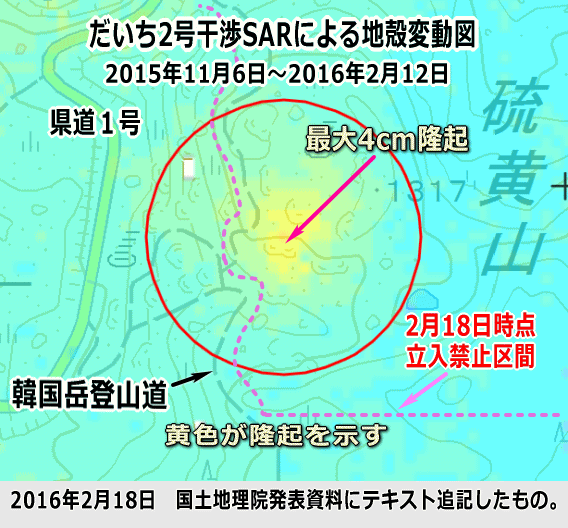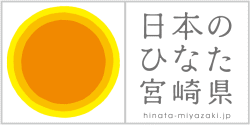えびの高原硫黄山周辺、有毒火山ガス(硫化水素・二酸化硫黄)分布図を見ての感想
Posted morimori / 2016.02.27 Saturday / 07:17
宮崎県は、えびの高原「硫黄山」の立ち入り禁止の範囲が適切かどうかを検証するため、2月26日から
硫黄山火口周辺で火山ガスの濃度の測定を始めました。
有毒な火山ガス(硫化水素・二酸化硫黄)の測定値が、宮崎県サイトで公開されてます。
今後、定期的に測定、硫化水素10ppm以上、二酸化硫黄5ppm以上が測定され、引き続き越えることが想定される場合、注意喚起や立入規制区域の設定などを検討するとのことです。
以下が2月26日のデーター(宮崎県サイトより)
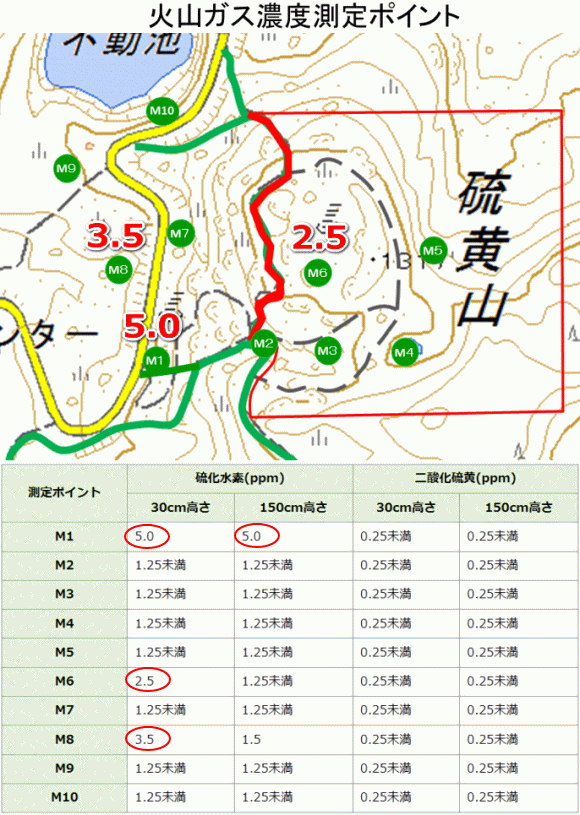
〜 硫黄山周辺、有毒火山ガス(硫化水素・二酸化硫黄)分布図 〜
この日のデーターで硫化水素の一番高いポイントは、現在の規制区域外の〔M1〕ポイント。県道一号線からの登山道入り口付近と思います。

M1ポイントの丁度下、県道1号(小林えびの高原牧園線)沿いの路肩には韓国岳への登山客がよく利用している路肩の駐車スペース(20台分程?)があります。
硫化水素は空気より重いので下へ降り滞留すると聞きます。
車で仮眠などしてたら、危ないのではないでしょうか?
駐車スペースの封鎖、停車禁止などの規制などは今のところ必要ないのでしょうかね?
10ppm(硫化水素の場合)は超えてないので問題ないのでしょうけど、現在の立ち入り規制内より規制外の方が高かったという測定結果を見て、気になりました。
私が、1月後半に行った際も、県道1号沿いあたりは結構硫化水素臭かったので、尚更気になります。
火山ガスの濃度は、当日の風向きなどにより変化するとは思いますが、不安を抱かないよう(現状の規制で問題無い旨)、測定データーを公開するにあたり、専門家の所見なども添えた方が良いのではないでしょうか。
福岡管区気象台によると、2月3日に職員が立ち入った際、簡易型警報器のアラームの計測できる上限の100ppmを一時的に超えたところもあったようです。
3月末まで、週3回、測定するとか。長引くようであれば、規制外の登山道付近、県道付近に有毒ガスをリアルタイムで測定、基準値を超えるといつでも警報が出せるようなものを設置した方が良いと思うのですが、口で言うのは簡単、難しいのでしょうかね?
カメルーンのニオス湖(火山湖)で住民1,700人と家畜3,000頭が窒息死
カメルーンのニオス湖(火山湖)では1986年に大量の二酸化炭素が一気に放出され住民1,700人と家畜3,000頭が窒息死している。ガスをなめてはいけない。
参考 → 消防防災博物館:ニオス湖 1986年ガス噴出 (カメルーン)
関連情報リンク
火山ガス事故防止のために└ 有毒な火山ガスから身を守るやめの手引き(環境庁自然保護局)
【追記】その後、翌日に1Km規制となりました。(次の記事参照)
県の危機管理サイトより・・
「硫黄山から概ね1kmの範囲が立入規制されたことから、当分の間、火山ガス濃度測定を中止します。(平成28年2月29日)」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/iouyamagasu20160226.html
委託された職員も怖いでしょう、今はやめたほうがいいです、リスキーです。
ミヤマキリシマが咲く頃(5月下旬〜6月初旬)までには落ち着いて欲しいのですが・・・。
動画 → えびの高原のミヤマキリシマ