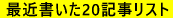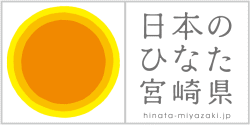西都古墳まつり 撮影記 [3/4] 炎の祭典
Posted morimori / 2017.11.06 Monday / 07:35
炎の祭典 Story 続き

上記写真は、3000pix幅に拡大します。
ニニギノミコト、コノハナサクヤヒメは、逢初川のすぐ近くに八尋殿を構え、新婚第一夜を迎えます。
しかし二人だけの生活も一夜限り、東の空が白みだした頃、ニニギの尊は、反乱する他族の平定の命を下され、愛する姫を一人残して、戦場へとむかわなければならないのでした。
尊を戦場へ見送って早、十月、あの一夜の思い出を胸に、待ち続けていた姫の元へ、尊は無事帰ってきました。
姫は喜びに泣き崩れながらも、尊の子を宿したこと、そして、今日にも出産することをつげました。
すると、尊は「たった一夜の契りで身ごもるはずがない。私の子ではない!」と姫が裏切ったとばかり、激しくなじるのでした。
待ち焦がれていた尊の冷たい言葉に打ちひしがれた姫は、疑いをはらす為に、茅で産屋をつくり、「尊のこならば、どんなに火の勢いが強くとも、きっと元気に生まれてくるはずです。」と言い残して中へ入りそとから火を放たせたのです。
燃えさかる炎の中から、姫の言葉どおり、ヒコホホデリノミコト、ホスセリノミコト、ホアカリノミコトの三人の皇子が次々と元気な産声をあげました。
こうして皇子の誕生をこの地の人々はたいへん喜びました。
現在、御陵墓(男狭穂塚塚・女狭穂塚)は、二人をまつる墓として伝えられております。
ニニギノミコト出陣
ニニギノミコトは、反乱する他族の平定の命を下され、愛する姫を一人残して、戦場へとむかわなければならないのでした。