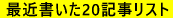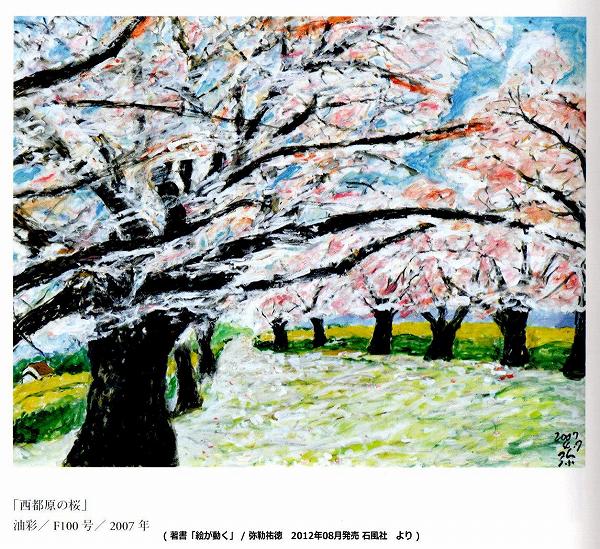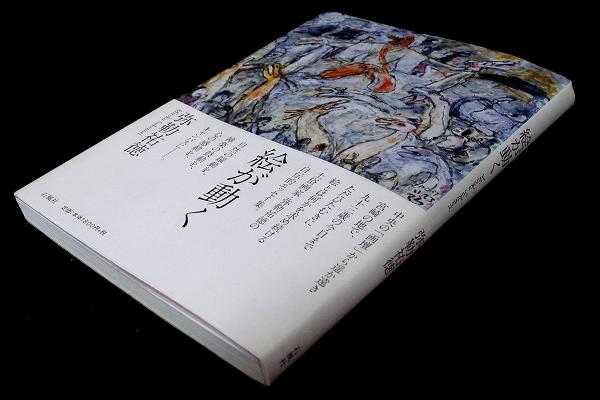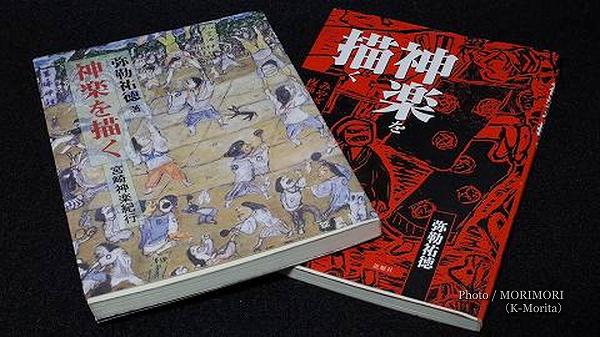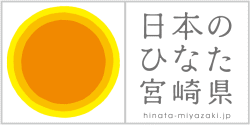田元神社 夏越の祓(夏越大祓)七夕飾り 風鈴回廊
Posted morimori / 2024.07.01 Monday / 23:11
田元神社(たもとじんじゃ)
鎮座地:宮崎市大字本郷南方3940-1(GoogleMap)(宮崎ブーゲンビリア空港の近く、県道367号沿い)
御祭神
- 木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)
- 彦火々出見命(ひこほほでみのみこと)
- 豊玉姫命(とよたまひめのみこと)
- 豊玉彦命(とよたまひこのみこと)
御由緒
明治12年(1879)3月16日、田元神社の氏子総代大坪儀三郎と同神社受持祠掌甲斐蔀は、寛治4年(1090)11月15日、恒久神社が児湯郡の都萬(つま)神社(西都市)祭神木花咲耶姫命を勧請したとき、本郷南方の高畑がその神輿掛の所となったことから、高畑の隣り田元に都萬神社祭神を勧請したと伝える、と鹿児島県令に報告している。
詳細は、村境に建立された田元神社 / 前田博仁を参照願います。
夏越の祓(夏越大祓)
宮崎市鎮座 田元神社
「夏越の祓(夏越大祓)」とは、6月末(6月30日)に行う祓の行事で、神社境内につくられた茅(ちがや)という草で編んだ輪「茅の輪」をくぐって罪や穢れを落とします。
丁度、一年の折り返しに前半の穢れを祓って無事に過ごせたことに感謝、後半も元気に過ごせるよう祈る行事です。
七夕と木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)
宮崎空港展示物 (宮崎の祭り) より「コノハナサクヤヒメ」
日本の七夕は、中国より7世紀頃に伝わった牽牛・織女の二つの星の伝説、短冊に歌や文字を書いて裁縫や書道の上達を願う風習と共に、日本古来の棚織女(たなばたつめ)の伝承と結びつき、宮中で行われたのが始まりだそうです。
棚織女(たなばたつめ)とは、神様に捧げる着物を織る、巫女的な要素を強く持つ女性。
木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)も棚織女(たなばたつめ)でもあったとされ、「七夕」にはコノハナサクヤヒメとニニギノミコトと逢初川で出会うという神話もさらに重なっているのでしょう。
そんな由縁ででしょうか、田元神社では境内で多くの七夕飾りを見ることが出来ます。
七夕飾りの短冊は例年、地元幼稚園保育園の園児たちが書いているようです。
田元神社 七夕飾り
田元神社 七夕飾り
七夕飾りは、早いところでは6月から飾り始めることもありますが、
本来は7月6日の夕方から夜に飾り、翌日には片付けるのが一般的のようです。
これは 「一夜飾り」 と呼ばれ、短冊に込めた願いが天に届きやすくなるといわれていますが・・
それでは、目に触れることも少ないので・・
早めに飾って、七夕を終えたら片づけるといった風習なのでしょうね。
茅の輪は、6月30日なのですが、7月初旬頃までは飾ってある神社が一般的のようです。
ちなみに、田元神社の前の道路、県道367号(中村木崎線)は車で良く通るのですが、7月12日車窓から見たところ、「茅の輪」と「七夕飾り」は、片付けてあったようです。