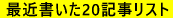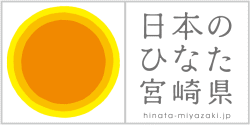【噴火・ガス留意】「えびの高原」と小林市を結ぶ県道1号、11/26〜限定再開
Posted morimori / 2022.11.09 Wednesday / 23:27
【追記】2023年12月6日 えびの高原(硫黄山)周辺の噴火警戒レベルはレベル2からレベル1へ引き下げられました。
県道1号の土日規定時間内の4輪車種限定通行も再開されます。
【追記】硫黄山付近の県道1号小林えびの高原牧園線は、昨年11月に、土日、時間、車両などの条件付きで通行再開しましたが、避難情報の基準を超える濃度の火山ガスの検出がが続いている為、6月3日より再び通行止めになります。
霧島連山・硫黄山(1317m)の噴火活動の影響で、一部区間の通行止めが続いている県道小林えびの高原牧園線(県道1号)について、県は11月26日(土)午前9時から通行を再開させると正式に発表した。
※ただし、通行は土日の中昼のみ、屋根のある車など諸条件がある。
(現時点での、これまでの硫黄山の火山活動状態状態を鑑み、開通による利便性(観光振興含む)と安全面、両者のバランスを考えた上での「落としどころ」だったのでしょう。)
硫黄山から見た県道1号の写真に新ルート追記
新ルートは、えびのエコミュージアムセンター付近から小林市方面へ約500m進んだ地点から噴気地帯を避けて約340mの区間。
県が事業費約1億5000万円をかけ盛り土工法で整備したもの。、
周辺の火山ガスの濃度が高まる時もあることなどを考慮し、安全性を確保するため以下となる。
土曜・日曜 午前9時〜午後5時の時間帯のみ規制を解除
平日や、祝日は通行止めを継続する。
通行出来る車両は、屋根がある自動車に制限、駐停車や車両からの乗り降りを禁止。
監視員を配置し安全対策を徹底。
再開後は、火山活動の状況を見ながら通行可能な日や対象車両の拡大の拡大を検討する方針。
池めぐり自然探勝路は、引き続きえびの高原〜不動池間は通行できません。
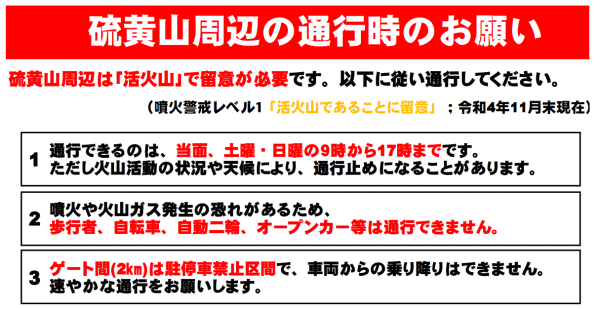



➡ 県道1号線(小林えびの高原牧園線)の通行止めを解除します!(宮崎県サイト)
オープンカー、バイク、自転車、人は通行不可となる見通しのようです。
おそらく・・
火山ガス(硫化水素など)の関係から、夜間は車中泊したりする可能性も出て来るので日中のみの解除にするのでしょう。
屋根のある自動車のみの制限も、窓を閉めて室内循環にすれれば通行中にガスを吸いこみ辛いといった観点からなのでしょう。
不動池付近から一部区間において、車の窓を閉めて、停まらずに走行するよう促されるものと思われます。
噴火活動が始まる以前も硫黄山付近でこういった表示を見かけた記憶がありますね。霧島温泉街に近くの地獄谷付近にもあったかと・・
えびの高原はバイクツーリングの方も多いので、ガスが早く落ち着いて、全車両通れるようになると良いのですが・・この辺りは判断が難しいのかも知れません。
おそらく、知らずにバイクで来て通行止に気づく方も出て来るのではないでしょうか? 生駒高原付近などに目立つ標識などの掲示が必要ですね。
登山する方は、夜明けと共に入山といった感じの方も少なくないと思うのですが、9時ゲート開門だと厳しいですね。
一連の規制について、十分な周知・徹底が必要かと思います。
2018年のMRT設置ライブカメラ映像 硫黄山の西側、県道一号線沿いで盛んに吹きはじめた噴気群

2018年4月20日・県道1号脇に噴気孔
活動が活発な当時、設置してあったライブカメラの映像をキャプチャしたもの
活動が活発な当時、設置してあったライブカメラの映像をキャプチャしたもの